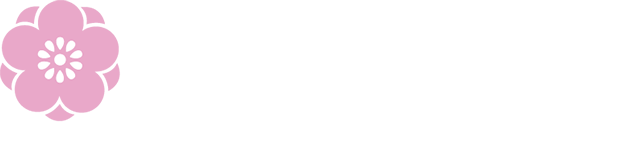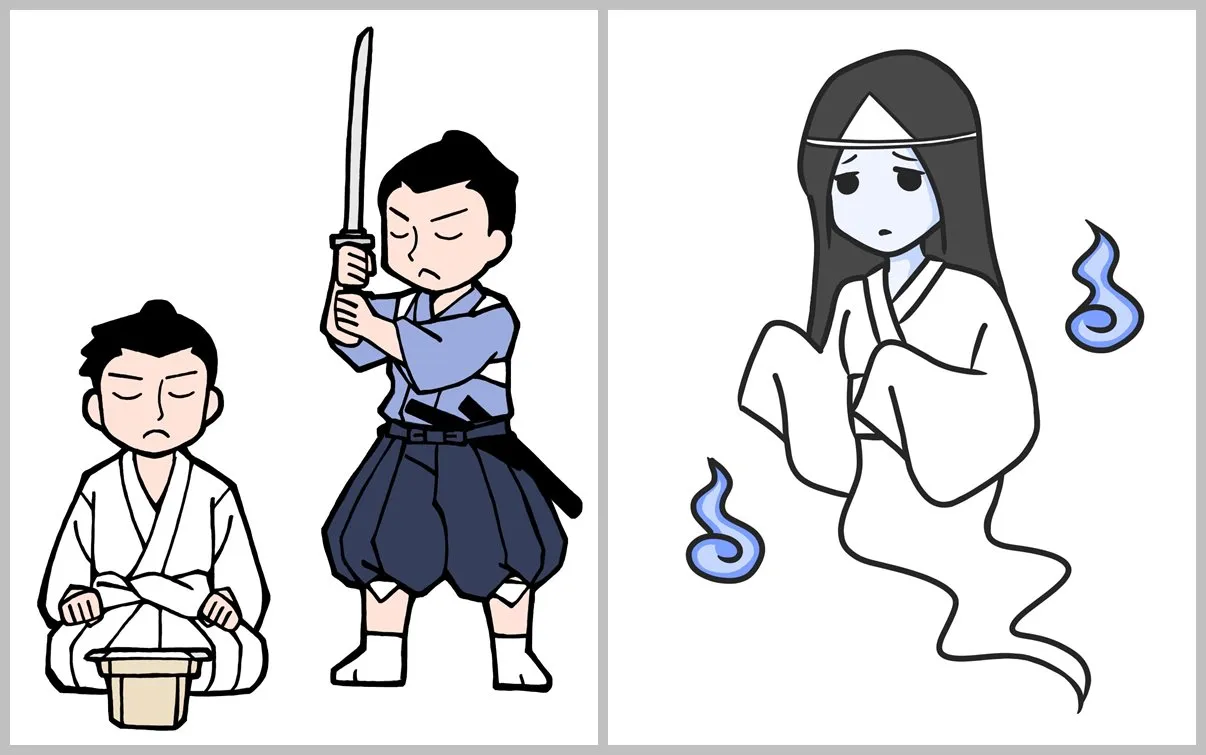弔う気持ちにふさわしいのはどっち?
お葬式の色と言えば「黒」と誰もがこたえるかもしれません。
だけど、歴史を振り返ってみれば、そうとも限らないのです。
もともと「クロ」というのは、暗い、黒いといった状態を表す言葉でした。
だから、死者が目を閉じて、光の入らない状態になった時の色といえば「クロ」の状態だったでしょう。
日本で喪服が最初に使われたのは、奈良時代だとされています。
けれど「日本書紀」によれば、この時、親族(ってこの頃も言ったのかなあ?)は白い装束を身に着けるのが通例とされているんです。
その後718年の「養老喪葬令」により、天皇が『錫紵(しゃくじょ)』という薄墨色の麻の喪服を着用するようになります。それをきっかけに、上流階級の人たちの間では、喪服と言えば薄墨色になっていくのです。
平安時代の代表作「源氏物語」では、喪に服したり、出家する人の衣装「純色(にびいろ)」という濃いねずみ色を使っています。
時と共にねずみ色が濃くなり、平安後期には黒い喪服になっていたようです。
それが、武士の時代となる室町時代には、また、白になっていくんです。
人々の心理的な動きを考えると、平安貴族には、「深い悲しみほど濃い色で表現」という色彩観があったのではないでしょうか?
特に濃い色は身分の高い人しか使えない「禁色」も多くありましたから。
その平安貴族の影響がなくなり、武士の時代になると「死というものは、肉体がなくなる、つまり色がなくなる」という感覚に変化していったのではないかと思うのです。
「喪の色は白」というのが長年定着していました。
時代劇でも、切腹する武士は白装束だし、幽霊も白い着物ですよね。
「死」と「白」には、心理的な結びつきがあります。
白という色は、浄化の色であり再出発の色。
肉体は滅んでも、次の肉体を得るまで「無」の状態でいるために「白」を喪の色とした色彩感覚は、今の私たちにも理解できるものですね。
それが、ふたたび「喪服は黒」になっていくのは、明治30年の皇室の葬儀に欧米諸国の賓客が参列したことがキッカケです。
彼らは、揃ってヨーロッパ王室式の黒い喪服を揃って着用していたのでした。
これを見た明治政府の首脳部は、慌てて黒い喪服をあつらえさせたとか。
大正期には、宮中参内での喪服は「黒を基調とする」と皇室令に明記されるようになりました。
この「喪服は黒」の流れが一気に広がったのには、戦争が関係しています。
第二次世界大戦で多くの人が亡くなり、喪服の出番が増えます。
そこで、貸衣装店は、汚れが目立たない黒を揃えるようになりました。
加えて、戦前は親族だけが着ていた黒の喪服を、冠婚葬祭の儀礼としての意識が高まり
参列者が全員黒で統一するといった風潮になっていくのです。
こう考えると、最初は、本当に死者を弔う気持ちから身に着けた「喪服」だったかもしれないけれど、戦後の貸衣装店の動き辺りからは、なにやら意図的なものを感じませんか?
常識は非常識の始まり
なんて言葉もあります。
「当たり前」だと思っていることを、ちょっと立ち止まって考えるクセをつけるのって、これからの時代、一番大事かもしれないと思ったりします。
あなたは、どう思いますか?